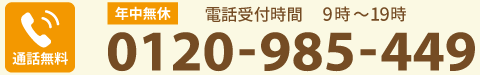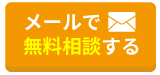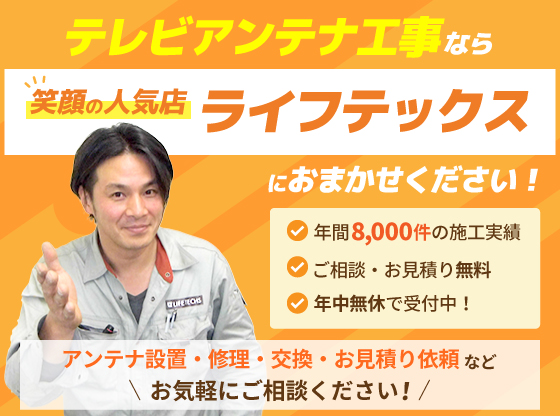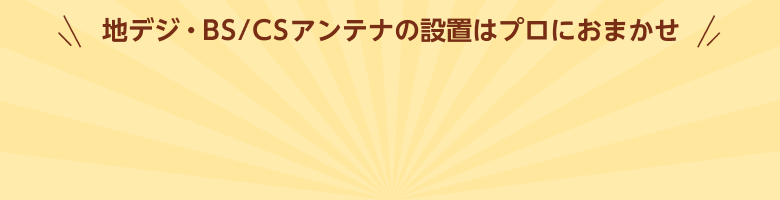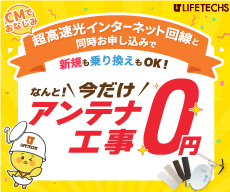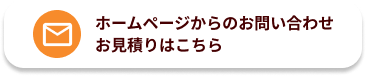地デジはいつから始まった?開始時期と完全移行の歴史を解説!

「地デジっていつから始まったんだろう?」
「実家のアンテナが相当古いけど、このまま使い続けて大丈夫なのかな…」
テレビに関する話題で、地デジの開始時期が気になった方もいますよね。
あるいは、ご自宅のアンテナが古く、地デジが開始された時期を調べることで、アンテナの設置時期を推測したいと考えている方もいるのではないでしょうか。
地デジ放送の開始時期と完全移行の歴史をまとめると、次の通りです。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 2003年12月1日 | 関東・近畿・中京の3大都市圏で地デジ放送開始 |
| 2006年12月1日 | 全国の県庁所在地で地デジ放送開始 |
| 2011年7月24日 | アナログ放送完全終了(東北3県は2012年3月31日) |
地デジ放送が開始されてから20年以上、アナログ放送完全終了からも10年以上が経過しました。
そのため、アナログ時代から使い続けているアンテナや、地デジ開始直後に設置したアンテナは、老朽化による倒壊リスクや700MHz電波障害などの問題が発生する可能性があります。
アンテナの平均寿命は10〜15年程度といわれているため、そろそろ交換を検討する時期といえるでしょう。
とはいえ、「どこに相談してアンテナ工事を依頼すればいいかわからない…」とお悩みの方もいますよね。
そういった方は、年間8,000件以上の施工実績を誇るライフテックスにおまかせください!
弊社は多くの施工実績があるため、高品質のアンテナ工事をご提供しております。
さらに部材をまとめて仕入れることで、低コストでのアンテナ工事を実現しています。
無料でお見積りを承っておりますので、まずはお気軽にご相談ください!
地デジはいつから始まった?開始時期と完全移行までの歴史
地デジ放送は2003年12月1日に開始され、2011年7月24日にアナログ放送から完全移行しました。
ただし、開始から完全移行までには段階的な展開があり、地域によって地デジが視聴できるようになった時期が異なります。
地デジの開始から完全移行までの流れを、次の表で確認しましょう。
| 時期 | 出来事 |
|---|---|
| 2003年12月1日 | 関東・近畿・中京の3大都市圏で地デジ放送開始 |
| 2006年12月1日 | 全国の県庁所在地で地デジ放送開始 |
| 2011年7月24日 | アナログ放送完全終了(東北3県は2012年3月31日) |
それぞれの詳細をひとつずつみていきます。
地デジ放送の開始は2003年12月1日
地デジ放送は、2003年12月1日の午前11時に、関東・近畿・中京の3大都市圏で開始されました。
この時点で地デジ放送を視聴できたのは、東京、大阪、名古屋を中心とした大都市圏のみでした。
地デジ化には、携帯電話の急速な普及により電波の周波数帯が不足していた背景があります。
テレビ放送が使用していた周波数帯を削減し、携帯電話などの通信用に再割り当てする必要があったのです。
また、デジタル化によって高画質・高音質な放送や、データ放送などの新しいサービスも実現できるようになりました。
当時は、地デジ対応テレビや地デジチューナーの購入が必要だったため、アナログ放送と地デジ放送が並行して放送される移行期間が設けられました。
全国への拡大は2006年12月1日
2006年12月1日には、全国すべての県庁所在地およびその周辺地域で地デジ放送が開始されました。
これにより、日本全国の主要都市で地デジ放送が視聴できるようになりました。
その後も、地方の中継局が順次整備され、徐々に地デジの視聴可能エリアが拡大していきました。
この時期には、「地デジカ」というシカのキャラクターが登場し、テレビCMや番組内で地デジへの移行を呼びかけるキャンペーンが展開されました。
地デジ対応テレビの普及を促進するため、エコポイント制度も導入され、地デジ対応テレビの購入を支援する施策が行われました。
アナログ放送完全終了は2011年7月24日
2011年7月24日の正午をもって、日本全国(東北3県を除く)でアナログテレビ放送が完全に停止されました。
これにより、日本の地上波テレビ放送は完全に地デジ放送へと移行しました。
ただし、2011年3月11日に発生した東日本大震災の影響を考慮し、岩手県・宮城県・福島県の東北3県については、特例措置として2012年3月31日までアナログ放送が継続されました。
アナログ放送が終了すると、地デジ対応のテレビやチューナーを持っていない世帯ではテレビが視聴できなくなったため、移行期間中に多くの世帯が地デジ対応機器を購入しました。
この完全移行から10年以上が経過した現在、当時設置されたアンテナも老朽化が進んでいる可能性があります。
なぜ地デジ化が必要だったのか?3つの理由
アナログ放送から地デジへの移行には、社会的な背景と技術的なメリットがありました。
地デジ化が必要だった主な理由は、次の3つです。
| 理由 | 内容 |
|---|---|
| 周波数帯の不足を解消 | 携帯電話の普及により電波が不足 |
| 高画質・高音質な放送の実現 | フルハイビジョンの高画質を提供 |
| 新しいサービスの提供 | EPGやデータ放送などの追加 |
それぞれの詳細をひとつずつみていきます。
理由①周波数帯の不足を解消するため
1990年代から2000年代にかけて、携帯電話が急速に普及しました。
携帯電話の通信には電波の周波数帯が必要ですが、当時はテレビ放送が多くの周波数帯を占有していました。
アナログテレビ放送では、VHF波(90MHz〜222MHz)とUHF波(470MHz〜770MHz)という広い周波数帯を使用していましたが、デジタル化によって映像データを圧縮できるようになり、使用する周波数帯を大幅に削減できるようになったのです。
地デジ放送では、UHF波のうち470MHz〜710MHzの周波数帯のみを使用します。
これにより、空いた周波数帯を携帯電話などの通信用に再割り当てできるようになり、電波の有効活用が実現しました。
理由②高画質・高音質な放送を実現するため
デジタル化により、映像をフルハイビジョン(1920×1080ピクセル)の高画質で放送できるようになりました。
アナログ放送時代の標準画質は640×480ピクセル程度でしたが、地デジではその約5倍の画素数を実現しています。
また、音声も高音質化され、5.1chサラウンド音声や、ステレオ音声による二か国語放送にも対応しました。
アナログ放送では、2.0chステレオと二か国語放送のどちらか一方しか選択できませんでしたが、地デジでは両方を同時に提供できます。
さらに、デジタル信号はノイズの影響を受けにくいため、電波状況が多少悪くても映像を復元可能です。
そのため、アナログ放送時代によく見られた、ゴースト(映像の二重化)や画面のちらつきなどが大幅に減少しました。
理由③データ放送など新しいサービスを提供するため
地デジ化により、テレビ放送と同時にデータ情報を送信できるようになりました。
EPG(電子番組表)では、リモコンのボタンひとつで約1週間分の番組表を確認できます。
録画予約も簡単になり、番組の放送時間が変更されても自動的に追従して録画できるようになりました。
また、リモコンの「dボタン」を押すことで、ニュースや天気予報、番組の詳細情報などを確認できるデータ放送も利用できます。
これらの新しいサービスは、アナログ放送では技術的に実現が困難でしたが、デジタル化により可能になったのです。
アナログ放送と地デジ放送の5つの違い
アナログ放送と地デジ放送には、さまざまな違いがあります。
主な違いを次の表で確認しましょう。
| 項目 | アナログ放送 | 地デジ放送 |
|---|---|---|
| 画質 | 標準画質(640×480程度) | フルハイビジョン(1920×1080) |
| 使用電波 | VHF波とUHF波 | UHF波のみ |
| アンテナ | VHFアンテナとUHFアンテナ | UHFアンテナのみ |
| 機能 | 基本的な視聴機能のみ | EPG、データ放送、双方向サービス |
| ノイズ | ゴーストが発生しやすい | ゴーストが発生しにくい |
それぞれの詳細をひとつずつみていきます。
違い①画質:標準画質からフルハイビジョンへ
アナログ放送の画質は標準画質(SD画質)と呼ばれ、画面解像度は640×480ピクセル程度でした。
一方、地デジ放送はフルハイビジョン(2K、FHD)で、画面解像度は1920×1080ピクセルです。
画素数で比較すると、地デジはアナログ放送の約5倍の精細さを実現しています。
また、アナログ放送時代のテレビは画面のアスペクト比(縦横比)が4:3でしたが、地デジでは16:9のワイド画面が標準となりました。
これにより、映画のような臨場感のある映像を楽しめるようになっています。
地デジ放送はフルハイビジョン(1920×1080ピクセル)ですが、放送局によっては実際に放送される際に1440×1080に変換されるケースもあります。
違い②使用電波:VHF波からUHF波へ
アナログ放送では、NHKや広域民放などの主要チャンネルはVHF波(90MHz〜222MHz)を使用し、東京MXや千葉テレビなどの独立放送局はUHF波(470MHz〜770MHz)を使用していました。
一方、地デジ放送では、UHF波の470MHz〜710MHzのみを使用します。
デジタル化により映像データを圧縮できるようになったため、使用する周波数帯を大幅に削減できたのです。
これにより、空いた周波数帯を携帯電話などの通信用に活用できるようになりました。
違い③アンテナ:VHFアンテナからUHFアンテナへ
アナログ放送時代は、主要チャンネルを視聴するためにVHFアンテナが必要でした。
VHFアンテナは、幅1メートル以上の大型で平べったい形状が特徴です。
さらに、独立放送局を視聴できる地域では、UHFアンテナも設置していました。
地デジ放送では、すべてのチャンネルがUHF波を使用するため、UHFアンテナのみで視聴できます。
そのため、アナログ放送時代にVHFアンテナのみを設置していた世帯では、UHFアンテナへの交換が必要となりました。
違い④機能:EPGやデータ放送の追加
アナログ放送では、テレビ番組を視聴する以外の機能はほとんどなく、番組表を確認するには新聞のテレビ欄やテレビ雑誌を見る必要がありました。
地デジ放送では、EPG(電子番組表)により、リモコン操作だけで約1週間分の番組表を確認できます。
また、リモコンの「dボタン」を押すことで、ニュースや天気予報、番組の詳細情報などを確認できるデータ放送も利用可能です。
これらの新しい機能により、テレビの利便性が大きく向上しました。
違い⑤ノイズ:ゴーストが発生しにくい
アナログ放送では、電波が建物などに反射すると、映像が二重に見える「ゴースト」という現象が発生しやすい特徴がありました。
また、電波が弱い地域では、映像がちらついたり、雪のようなノイズが入ったりするケースもありました。
地デジ放送では、デジタル信号にノイズが混入しても、ある程度のレベルであれば受信機側で信号を修復できます。
そのため、アナログ放送時代によく見られたゴーストやちらつきなどの画質劣化が大幅に減少しました。
ただし、デジタル信号の修復が困難なレベルまでノイズが増えると、映像にブロックノイズ(画面がモザイク状に乱れる現象)が発生したり、まったく映像が映らなくなったりするケースもあります。
アナログ時代の古いアンテナを使い続けるリスクとは
「古いアンテナでも地デジが映っているから問題ない」と考えている方もいるかもしれません。
しかし、アナログ時代のアンテナや、地デジ開始直後に設置したアンテナを使い続けることには、次のようなリスクがあります。
| リスク | 内容 |
|---|---|
| 700MHz電波障害で画面が乱れる | スマートフォンの電波を受信して画面が乱れる |
| 老朽化による倒壊・落下 | 台風や地震で倒壊・落下する危険性 |
| 受信感度の低下 | アンテナの劣化で画質が悪くなる |
それぞれの詳細をひとつずつみていきます。
リスク①700MHz電波障害で画面が乱れる可能性
アナログ時代のUHFアンテナは、地デジ用のアンテナよりも受信できる周波数帯の幅が広い設計です。
しかし、アンテナの設計により、スマートフォンなどで使用される700MHz帯の電波を受信してしまう可能性があります。
700MHz帯の電波をアンテナが受信すると、テレビ映像にブロックノイズが発生したり、画面が乱れたりする「700MHz電波障害」が起こります。
とくに、アンテナの信号を増幅するブースターを使用している場合、ブースターが不要な電波まで増幅してしまうため、症状が悪化してしまうのです。
現在の地デジ専用アンテナは、700MHz帯の電波を受信しないよう設計されているため、700MHz電波障害は発生しません。
古いアンテナを使い続けている場合は、最新の地デジアンテナへの交換を検討しましょう。
リスク②老朽化による倒壊・落下の危険性
アンテナは屋外に設置されるため、常に雨風や紫外線にさらされています。
20年以上前に設置されたアンテナは、金属部分の腐食やサビが進行し、強度が大幅に低下している可能性があります。
とくに、アンテナを固定している支線(ワイヤー)やマスト(支柱)が劣化すると、台風や地震などの災害時に倒壊する危険性が高いので危険です。
アンテナが倒壊すると、屋根を傷つけたり、隣家に被害を与えたりする可能性があります。
アンテナの平均寿命は10〜15年程度といわれているため、設置から15年以上経過している場合は、早めの交換を検討しましょう。
リスク③受信感度の低下で画質が悪くなる
アンテナの素子(電波を受信する部分)が経年劣化すると、受信感度が徐々に低下します。
受信感度が低下すると、テレビ映像にブロックノイズが発生したり、一部のチャンネルが映らなくなったりします。
受信感度の低下は徐々に進行するため、気づきにくいのが特徴です。
しかし、ある日突然テレビが映らなくなることもあるため、定期的なメンテナンスや交換が重要です。
とくに、地デジ完全移行から10年以上が経過した現在、2011年頃に設置したアンテナは交換時期を迎えています。
地デジアンテナの工事をするならライフテックスにおまかせ!
古いアンテナの交換を検討している方は、年間8,000件以上の施工実績を誇るライフテックスにおまかせください!
- 年間8,000件以上の施工実績で安心
- まとめて部材を仕入れているため費用が抑えられる
- 8年間の工事保証で長期的に安心
- 見積もり無料で気軽に相談できる
弊社は多くの施工実績があるため、高品質のアンテナ工事をご提供しております。
さらに部材をまとめて仕入れることで、低コストでのアンテナ工事を実現しています。
ライフテックスのアンテナ工事を受けると、古いアンテナの不安から解放されて、安心して高画質のテレビが楽しめるようになりますよ!
無料でお見積りを承っておりますので、まずはお気軽にご相談ください!
新築や引っ越しのタイミングならLAN工事もまとめて依頼しよう!
新築住宅への引っ越しや、リフォームのタイミングでアンテナ工事を検討している方は、LAN配線工事も同時に依頼することをおすすめします。
アンテナ工事とLAN配線工事をまとめて依頼すると、個別に依頼するよりも効率的で、費用も抑えられます。
とくに、新築や引っ越しのタイミングであれば、壁の中に配線を通す隠蔽配線工事もスムーズに行えます。
ライフテックスでは、アンテナ工事・エアコン工事・LAN工事をセットでお得に依頼できる新築応援キャンペーンも実施しています!
新生活をスタートする際に、テレビもインターネットも快適に使える環境を一度に整えませんか?
地デジアンテナの種類と選び方
地デジアンテナには、複数の種類があります。
ご自宅の電波環境や、外観へのこだわりに合わせて、最適なアンテナを選びましょう。
| アンテナの種類 | 特徴 |
|---|---|
| 八木式アンテナ | 受信感度が高く弱電界地域でも安心 |
| デザインアンテナ | 外観を損ねずスタイリッシュ |
| ユニコーンアンテナ | デザイン性と受信感度を両立 |
それぞれの詳細をひとつずつみていきます。
八木式アンテナ:受信感度が高く弱電界地域でも安心

八木式アンテナは、魚の骨のような形状が特徴的なアンテナです。
屋根の上に設置することが多く、日本でもっとも普及しているアンテナの種類となっています。
八木式アンテナの最大の特徴は、受信感度の高さです。
素子数(電波を受信する部分の数)が多く、電波の弱い弱電界地域でも安定してテレビを視聴できます。
また、アンテナ本体の価格が比較的安価なため、コストを抑えたい方にもおすすめです。
ただし、屋根の上に設置するため外観に影響を与えやすく、風雨の影響も受けやすいというデメリットがあります。
八木式アンテナについてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
デザインアンテナ:外観を損ねずスタイリッシュ

デザインアンテナは、長方形の箱型をした平面アンテナです。
外壁に設置することが多く、住宅の外観を損ねにくい特徴があります。
カラーバリエーションも豊富で、白・ベージュ・茶・黒などから、外壁の色に合わせて選べます。
八木式アンテナに比べてコンパクトなため、景観を重視する方や、新築住宅に設置する方に人気です。
ただし、設置場所が屋根よりも低い位置になるため、電波の弱い地域では設置できない場合があります。
デザインアンテナについてさらに詳しく知りたい方は、こちらのページを参考にしてください。
ユニコーンアンテナ:デザイン性と受信感度を両立

ユニコーンアンテナは、2017年に登場した比較的新しいタイプのアンテナです。
ポール状のスタイリッシュな形状が特徴で、360度どこから見ても景観を損ねません。
屋根の破風板(屋根の端の板)や外壁の高い位置に設置できるため、デザイン性と受信感度を両立しています。
八木式アンテナほどの受信感度はありませんが、デザインアンテナよりも高い位置に設置できるため、中電界地域でも安心して使用できますよ。
デザイン性を重視しつつ、確実な受信を実現したい方におすすめです。
ユニコーンアンテナについてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
地デジに関するよくある質問
地デジやアンテナに関する、よくある質問にお答えします。
アナログ時代のVHFアンテナで地デジは見られる?
|
VHFアンテナでは地デジ放送を視聴できません。 アナログ放送時代の主要チャンネルはVHF波を使用していましたが、地デジ放送ではUHF波のみを使用しています。 そのため、VHFアンテナのみを設置している場合は、UHFアンテナへの交換が必要です。 ただし、アナログ時代に独立放送局を視聴するためにUHFアンテナも設置していた場合は、そのUHFアンテナを地デジ用として使用できる可能性があります。 とはいえ、アナログ時代のUHFアンテナは老朽化や700MHz電波障害のリスクがあるため、最新の地デジ専用アンテナへの交換をおすすめします。 |
地デジアンテナの寿命はどのくらい?
|
地デジアンテナの平均寿命は、10〜15年程度です。 ただし、設置環境によって寿命は大きく変わります。 たとえば、海沿いの地域では塩害により金属部分の腐食が早く進むため、寿命が短くなる傾向があります。 また、台風が多い地域や積雪の多い地域でも、アンテナへの負担が大きくなり、寿命が短くなる可能性があります。 定期的にアンテナの状態を確認し、サビや変形が見られる場合は、早めに交換を検討しましょう。 |
地デジ対応テレビなら古いアンテナでも映る?
|
地デジ対応テレビを購入しても、アンテナがVHFアンテナのみの場合は、地デジ放送を視聴できません。 地デジ放送を視聴するには、UHFアンテナが必要です。 また、アナログ時代のUHFアンテナをそのまま使用している場合でも、老朽化により受信感度が低下している可能性があります。 テレビ映像にブロックノイズが発生したり、一部のチャンネルが映らなかったりする場合は、アンテナの交換を検討しましょう。 |
4K8K放送を見るにはアンテナ交換が必要?
|
地デジの4K8K放送を視聴する場合は、基本的にアンテナ交換は不要です。 ただし、BS/110度CSアンテナで4K8K衛星放送を視聴する場合は、4K8K対応のBS/110度CSアンテナへの交換が必要です。 従来のBS/110度CSアンテナは、4K8K放送で使用される高い周波数帯に対応していないためです。 また、アンテナから各部屋への配線や、分配器なども4K8K対応のものに交換する必要があります。 4K8K放送の視聴を検討している方は、専門業者に相談して、必要な工事を確認しましょう。 |
まとめ
地デジ放送の開始時期と完全移行の歴史についておさらいしましょう。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 2003年12月1日 | 関東・近畿・中京の3大都市圏で地デジ放送開始 |
| 2006年12月1日 | 全国の県庁所在地で地デジ放送開始 |
| 2011年7月24日 | アナログ放送完全終了(東北3県は2012年3月31日) |
地デジ放送が開始されてから20年以上、アナログ放送完全終了からも10年以上が経過しました。
アナログ時代のアンテナや、地デジ開始直後に設置したアンテナは、老朽化による倒壊リスクや700MHz電波障害などの問題が発生する可能性があります。
アンテナの平均寿命は10〜15年程度といわれているため、設置から15年以上経過している場合は、交換を検討する時期です。
とはいえ、「どこに相談してアンテナ工事を依頼すればいいかわからない…」とお悩みの方もいますよね。
そういった方は、年間8,000件以上の施工実績を誇るライフテックスにおまかせください!
弊社は多くの施工実績があるため、高品質のアンテナ工事をご提供しております。
さらに部材をまとめて仕入れることで、低コストでのアンテナ工事を実現しています。
また、壁の中にケーブルを通す隠蔽配線工事や、屋根裏へのアンテナ設置など、複雑な工事にも対応可能です。
無料でお見積りを承っておりますので、まずはお気軽にご相談ください!